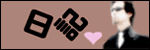2008年11月23日 山中優著『ハイエクの政治思想』
 山中優著『ハイエクの政治思想』
山中優著『ハイエクの政治思想』
──本書はハイエクの中期〜後期(コレは私が大まかに、かつ感覚的に分類した区分ですが)の理論変遷を適格に整理した好著であろうと思います。
本書の内容をかいつまむと以下のようになるでしょう。
『隷従への道』や『自由の条件』を著した頃のハイエクの自由論は、ある種楽観主義的な面が強かった。彼は「個人的自由」というものはそれ自体で「至高の価値」を有するものであるとして、人々がそれを尊重することによって広く繁栄がもたらされるのだと強調していたのです(このようなタイプの自由論を著者は「帰結主義的な義務論」と呼びます。つまり、人々が自由を尊重していると結果的に繁栄がもたらされるんだという、ある意味では穏健な考え方です)。しかし、ハイエクは次第にその態度を変化させてゆきます。そうして後期の『法と立法と自由』を世に出した時点にあっては、結果としてもたらされる繁栄について悲観主義的な要素を伴って強調するといった風になったのでした。つまり、それはこういうことです。その時期の彼は「義務論的な帰結主義」を唱える様になっていて、「自由(を守るための正義の諸ルール)」を維持しなければ、結果として我々の「生存のチャンス」は喪失してしまうぞという意見、要するに、恐ろしい帰結を主張することによって強硬的に「自由」を尊重すべしと訴えかけるものへと変化していたというわけなのです。自由の放棄=死だというんです。
なぜこのような変化を遂げたのでしょうか。
著者はそこでハイエクの人間観を指摘します。すなわち、ハイエクが「部族社会の情緒」と称した人間に内在する性質──身内での親密さと外部の者に対する敵愾心、大胆に言ってしまえば、閉鎖的ってコト──が問題となってくるのです。その存在のために、K.ポパーが「開かれた社会」といったような空間、すなわち市場秩序に対して人々は適合的であるとはいえなくなるのです。なぜなら、そこは互いに異なる目的を有する諸個人が、各自の目的を達成する為に雑然と入り乱れる場所であって、しかも必ずしも結果を保障されたわけではなく、常に失敗の可能性と隣り合わせにありながら、勇敢に活動することを要求される冷淡な場所だからです。いわば実力と運に左右される不確実な要素な支配的で、未知の者と共存せねばならない市場という空間にいることに対して、人々は元来「弱い不適合性」にある。だから、彼らは自ずと市場における自由な活動から距離を置いてしまうといった事態へと向かいかねない(「部族社会」への憧憬による先祖帰り)。ハイエクはこの点(自由社会が必然的なものではないということ)に苦悩しました。すなわち、潜在的に「部族社会の情緒」を秘めた諸個人は、冷酷さをもつ市場における自由な活動を好まず、己の安寧を政府権力によって満たしてもらおうと願う。その時、生じてくるものはといえば、「福祉国家」の名の下における(特殊な集団利益への偏愛に満ちた)利益誘導型のデモクラシーに他なりません。ここに至り市場における自由な活動もそのスーパーパワーに依存するものとなり、社会の発展は望めなくなります。行き詰まっちゃうのだ。窮屈な生存を余儀なくされてしまう。窮極的には自由が喪失してしまうのです。自由の放棄=死の意味するトコロです。こういう風に考えていけば、ハイエクが悲観主義的になったのも当然ではないでしょうか。そして、こうした点を踏まえるならば、彼の議会制改革論も、「部族社会の情緒」に淵源する恣意的な権力を抑制するために「法の支配」を徹底させることを目的として打ち出されたものであると考えることができましょう。それは当然の成り行きだったのです。
本書において最も印象的だったのは、ハイエクが市場秩序の出現に関して、その起源を宗教的なタブー(著者はそれをヘーゲルの「理性の狡知」に倣って「タブーの狡知」と称する。モチロン、この二者に込められている含意は大きく異なるけれども)に求めたという指摘がなされてあった点です。私はハイエクに関して、その著作において宗教との結びつきが非常に稀薄な様に感じていました。ですから、本書にて記されていたハイエクと宗教の問題については、新たな発見をしたといった感を受けたのです。また、彼が市場秩序の正当性の根拠としても宗教的な規範を必要としていたのではないか、との著者の指摘は大変興味深いものがありました。本書に補論として所収されている「文化的進化論の批判的継承をめぐって その近年の動向についての素描」で、著者は以下の如く記すことで、その結びとしています。
市場において「どうして自分の所得や資産が増減しなければならないのか、どうして自分が一つの職業から他の職業へと転業しなければならないのか、欲しいものを手に入れるためにどうして自分だけこんなに苦労しなければならないのか」──こうした問い、すなわち市場における“なぜ”という問いは、やはり人間として、どうしても発せずにはいられない性質のものだろう。確かに一方でハイエクは、そうした問いに明確な答えを見つけることはできないと述べていた。それは各人の腕と運とによって決まるとしか言いようがない、それが複雑現象たる市場の本質である──という冷淡な主張をわれわれに突きつけていたのである。にもかかわらず、そのハイエクが、市場における“なぜ”という問いに答えてくれるものとして、結局は宗教的規範のもつ力に依拠せざるを得なくなったのであった。この事実は、マルクス主義なきあと“宗教の復讐”(ケベル)に揺れる現代において、自由市場経済の今後を考えていく上で、非常に大きな重みを持っているのではないか──筆者にはそのように思われてならないのである。(二二九〜二三〇頁)
著者の見解に同意します。市場と宗教の問題──日本だとそうでもない問題かもしれませんが、欧米諸国においては殊に重要な問題となるでしょう。それ故に今後この二者の間に如何なる関係が生じてくるかによって、自ずと我が国の政治・経済・文化の在り方にも何らかの影響が生じてくるのではないかと思うのです。