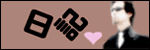2008年04月06日 片目物語
山の老人は自然のお喋りが大好きでした。山々の囁き、大地の叫び、風の励まし、雨の眼差し、そんなものたちといつも触れ合っていられることに幸福感を味わっていました。老人に家族はありませんでした。結婚もしませんでした。両親は老人が青年の頃に天国か地獄かに旅立って行ったので、それより今に至るまで一人で、自然と一緒に春の日差しの日も初夏の緑の日も晩秋の落葉の日も冬の白の日も過ごして来たのです。寂しいとは思ったこともありましたが、その度に自然の声援を聞いたので、老人は気力が湧いてきて畑仕事もどんどんこなすことができたのです。
老人に口は必要ありませんでした。彼は自然のお喋りが大好きでしたので、彼らの声を聞き逃さない耳だけがあれば、心は膨らんだのです。
山は言います。「お爺さん、心細くはないかい」
大地も言います。「お爺さん、怖くはないかい」
風も負けじと言います。「お爺さん、寒くはないかい」
雨も加わって言います。「お爺さん、冷たくはないかい」
老人は久しぶりに声を出しました。「ワシは平気じゃよ。いつも君たちが傍にいてくれるからのぉ」
山が言いました。「でも、お爺さんの近くにばかりいるわけではないよ」
大地も言いました。「お爺さんは自分を誤摩化しているだけじゃないのかい」
風も言いました。「お爺さんはあっちの空ばかり見て、こっちの空の色を知らないんじゃないのかい」
雨が最後に言いました。「お爺さんは何のお話もしてくれないや。いつも聞いているだけで、それじゃ僕らは面白くないやい」
老人は何かの言葉を口元まで運んできたのですが、ぐっと抑えて下を見ました。地面が初めて冷たく感じました。地面を温かくしたいと思いましたが、どうすれば良いかは知りませんでした。
山と風が言いました。「お爺さんと僕たちは近いようで遠いのかもね」
大地と雨が言いました。「隣町のお爺さんは物知りだからいつも楽しいんだ。でもこっちのお爺さんは没個性的過ぎていけないよ」
そうして自然は隣町の老人を目がけて走り去って行きました。
老人は独り取り残されたのですが、彼らがまた戻ってくるのを待とうと思いました。彼は喋ることがありませんでしたが、気持ちだけはずっと同じままでいたいと思ったのです。
老人は生き抜くことがヘタクソでした。
皆が隣町の老人から離れて戻ってきたときには、もうこっちの老人は天国か地獄かに移り住んでいたのです。それで山は老人を悼んで花を目一杯咲かし、大地は老人が生きていた場所をしっかりと包み込み、風は沢山の種を運んできて、雨は植物が生き抜けるように思い切り水を分け与えたのです。
これが片目の老人と自然のお話です。