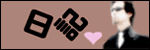2007年07月15日 吉田満と戦後社会
「ガンバレ、ガンバレ」甲板ヨリ、耳ヲ突キ刺ス兵ノ声
彼ラ、ワガ苦闘ノ一切ヲ目撃シイタルナリ 真情ニ貫カレタルコノ激励
「生キロ、生キロ、ココマデ来テ死シテ相済ムカ、死ンデ許サレルカ」身ウチニ叫ブ声ス
初メテ、真ニ初メテ、生ヲ求ムル意地、カット開ク
生キタキ希求ニ非ズ、生キズンバヤマザル責務ナリ
肉体消エントシテ魂魄ヨウヤクニ燃エ、スベテヲ奪ワレテタダ真ニ己レナルモノ残ル
血、油ニマミレ、縄ニカラマレシワレニアルハ、カノ消エザル火ノミ
コレゾワガ死スベキ窮極ノ時、死ヲ許サレン至福ノ時
故ニコソマタ果敢ニ生クベキ時
 吉田満の不朽の名著『戦艦大和ノ最期』の一節である。(講談社文庫版の一四五〜一四六頁)
吉田満の不朽の名著『戦艦大和ノ最期』の一節である。(講談社文庫版の一四五〜一四六頁)
「天一号作戦」により沖縄に向けて特攻出撃した大和は、昭和20年4月7日14時20分過ぎに連合軍の攻撃を受け、鹿児島県坊ノ岬沖90海里の地点に沈没した。
上に引いた一節は、大和撃沈後、海面に漂流していた吉田がまさに救出されんとしている場面を描いたものである。
特攻出撃という事態の真っ直中に身を置き、そして連合軍の熾烈な空爆との戦闘に死力を尽くし、最早死だけを想定していた心境が、突如としてここで変転する。死ぬ為に生きる、この瞬間に己の生命の全てを賭ける、戦闘中にー命のやり取りをしている瞬間にー戦争の善悪などを問う余地はなく、ただ美しく死ぬために闘い、己の生の価値というものをそこに植え付けようと必死でもがいていた吉田の中に、死への意志を放棄し、限りない生への希求をもたらした瞬間。ー確かにそれは「瞬間」であったが、この時の吉田は明確に「戦死する」という自らにとって宿命的ともいえる願望を振り切っている。
初版のあとがきで、吉田は次のようにいう。
この作品の中に、敵愾心とか、軍人魂とか、日本人の矜持とかを強調する表現が、少なからず含まれていることは確かである。だが、前にも書いたように、この作品に私は、戦いの中の自分の姿をそのままに描こうとした。ともかくも第一線の兵科士官であった私が、この程度の血気に燃えていたからといって、別に不思議はない。我々にとって、戦陣の生活、出撃の体験は、この世の限りのものだったのである。若者が、最後の人生に、何とか生甲斐を見出そうと苦しみ、そこに何ものかを肯定しようとあがくことこそ、むしろ自然ではなかろうか。(同上書一六七頁)
吉田は大和の乗組員として、間違いなく戦争の中に「何とか生甲斐を見出そうと苦しみ、そこに何ものかを肯定しようとあが」いていた。
戦闘が終わり、大和は轟沈し、暗黒のような海中に投げ出された吉田に助けの手が差し伸べられたとき、「コレゾワガ死スベキ窮極ノ時、死ヲ許サレン至福ノ時/故ニコソマタ果敢ニ生クベキ時」との感を吉田に抱かしめる“転機”となったものは何であったか。
決して意識が戦場から離脱したり、無類の安心感を得たというわけではなかろう。一度は死を必定のものと受諾し、それならばそこに向かって精根尽き果てるまでエネルギーを注入せんと試みた者だけが手にすることのできる死に対するある種の希望と、死にゆく己に対する信頼感というものがあるはずだ。しかしながら、そうした思いは、生きとし生けるものの深奥に根ざす本能的な防御意識とどこかで交わることがあるのを忘れてはなるまい。すなわち、一度は死を決意し、承認するがゆえに湧き出てくる生への憧憬がそれである。死への意志に身を包みながらも、その綻びの隙間からこぼれ落ちてくる生への渇望。吉田ならずとも、死と否応無く対峙せねばならぬ状況下に佇むことになった者ならば、誰しもが避けては通れぬ葛藤がある。それが顕在化した瞬間が、他ならぬ上記の場面である。
一度は死への意志を放棄したかのように見える吉田であるが、彼の胸のうちもまた二転三転する。その葛藤する様を拾ってみよう。
特攻作戦終結ヲ耳ニシテ、生死ノ関頭ヲ踏ミ越エタル歓喜ナシ
死ハナオ間近ニアリ、生コソムシロ苦痛ナリ 克己ナリ(同上書一四九〜一五〇頁)
艦スデニ九州西岸ヲ走ル 陽光沁ミワタル眸ニ、内地ノ山ノ、麗ラカナル美シサ
思ワズ嘆声アガル「生キルノモ、ヤッパリイイナア」
(中略)
生還ハ我ラガ発意ニ非ズ、僥倖ノ結果ナリトミズカラヲ慰ムルモ、ナオ後メタサ消エズ我ラ救ワレタルハ、正シキカ(同上書一五八頁)
吉田は、自らの葛藤を臆するところ無く吐露した『戦艦大和ノ最期』を著したことにより、次のような問題と向き合わねばならなかった。
戦争の中の赤裸々な自分を、戦後の立場に立つ批判をまじえることなく、そのまま発表するという姿勢からは、戦後時代をいかに生きるべきかについてわれわれに訴えるものがないという指弾は、初版が公にされて以来絶えずおこなわれてきた。(同上書一七六頁)
「戦争の中の赤裸々な自分を、戦後の立場に立つ批判をまじえることなく、そのまま発表する」といういわば一度全てを受け入れた所からの発言、それは吉田が戦闘経験によって手に入れた唯一の戦争と向き合う手段であったのである。観念的な反戦活動や実態を知らない平和主義者の叫び声を軽薄なものと見なし、己の肉体と魂に刻み込まれた「記憶」によってのみ、戦後の自分を確立する。死とは何であるか、生とは戦争とは平和とは何であるか… すべてを実体験によって学んだ吉田の中には、揺るぎない視点が確立されているように思われる。それは、以下のような発言の中にも顔を覗かせている。
われわれは戦争のために死ぬことによって、ようやく後世への発言を認められる世代であった。(中略)戦中派世代の生き残りは、生き残ったことで存在を認められるのではない。(『戦中派の死生観』)
吉田は戦闘によって、肉体的な死を迎えることはなかった。だが、彼は命を賭けた戦争経験を通じて、死の寸前に迫ることで、死ぬことの意味も生きることの意味も悟ったのではなかろうか。つまり、戦争による死と生が表裏一体であるということの実感ー「いかに死ぬか」は「いかに生きるか」と同義であるということの発見ーは、吉田にとって意識的な上で死の経験に等しいものであったといい得る。戦争を経験することによってしか生まれ出てこなかったであろうそのような新たな思想(戦争に全身全霊をかけた己を肯定し、全てを受け入れた所からの働きかけ・戦争の真っ直中で、生きようとすることにも、死を欲することにも、意味を見出した得た経験からの働きかけ)を獲得した吉田は、自らの体験を普遍化し、その中に自己を確立させることのみが、戦後社会に対する有効な身の施し方であると確信するに至ったのだ。そしてまた、これこそが戦争を通じて「何とか生甲斐を見出そうと苦しみ、そこに何ものかを肯定しようとあが」いていた彼の手にした至上ともいうべきものであった。
吉田の以下の言に注目してみよう。
戦後派にとっては、戦争対平和は、ただ戦争は憎悪すべきもの、平和は歓迎すべきものとの当然かつ単純な対比関係として片づけられ、その仮りの保証の上に、彼ら自身の生涯の逸楽が追い求められているのであろう。戦中派にとっては、戦争対平和は、まず何よりも痛みを持った、自分の生の意味を賭けた問題である。戦後の平和が、例えば気持ちのいい議論や景気のいい宣伝とは全く無縁の、泥まみれな、血みどろの世界であることを身をもって知らされているのである。(『平和への巡礼』)
吉田本人もあとがきで述べているように、『戦艦大和ノ最期』は戦争文学である以上に、吉田満というひとりの人間が、戦後社会の中に己の意識を植え付けようとした最初の一歩に他ならない。
戦後、我々は意識の上での戦争問題とばかり対決してきた。その半狂乱のような状況の中で、吉田がやらんとしたことの重要性を改めて問い直してみる必要もあるのではないか。観念的な戦争問題ではなく、実態としての戦争を通過してきた者の声から意識を再構築するという作業が、もう一度顧みられても良いはずである。ただし、それは大変な勇気を伴う所行でもある。今後、我々はその勇気をどれほど持ち得るか。持ち堪えられ得るか。