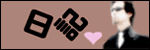2008年11月04日 「復活のための序曲」
 これは『ビルマの竪琴』についての文章です。
これは『ビルマの竪琴』についての文章です。
『ビルマの竪琴』は文学者である竹山道雄氏が子供向けに書いた童話です。でも、二十歳から三年間を無為に見過ごした私が読んでも、心は風に吹かれた蓮花の花の如くサワサワと動きます。これはとても感動的なお話です。これは戦争と音楽のお話です。ビルマ(現ミャンマー)に駐屯する兵隊サンたちを描いたお話です。兵隊サンたちは歌を歌うのです。戦火の下でも、終戦後に捕虜として収容所に収監されても、みんなみんな合唱するのです。「はにゅうの宿」「春らんまん」「庭の千草」といった曲を精一杯、精一杯歌うのです。それが彼らの隊の士気を鼓舞するのです。
主人公の水島上等兵は竪琴を上手に上手に弾きます。他の隊員からの信頼も厚い立派な兵隊さんです。隊長が水島上等兵に寄せる信も殊更強いものがありましたので、彼は水島にある命を託します。それは終戦を告げられてもなおイギリス軍を相手に抗戦する友軍の説得という任務です。隊長の思いはこうです。
国は廃墟となり、自分たちの身はこうした万里の外で捕虜となる──。これは考えてみればおどろくべきことだ。それだのに、私は、これはどうしたことだ──、とただ茫然自失するばかりである。それをはっきりと自分の身の上に起こったことだ、と感ずることすらできない。ただ手からも足からも力が抜けてゆくような気がする。……(中略)……そうして、もし万一にも国に帰れる日があったら、一人ももれなく日本へかえって、共に再建のために働こう。いま自分のいえることは、これだけである。
水島上等兵は、依然として頑に抗戦を続けようとする仲間を説得し、「共に再建のために働こう」とのメッセージを伝えるため、仲間の元を外れて単身三角山へと向かいます。他の兵隊サンたちは水島上等兵を信頼していましたから、きっと彼が友軍の者たちを説き伏せて、また我らの前に姿を現すであろうと信じています。信じていました。しかし、水島上等兵は帰って来ません。一月が過ぎて行きましたが、水島上等兵は戻らないのです。さすがに仲間も心配し始めます。まさかあの水島が? いや、そんなことはない。そうだ、あの水島に限って。──けれども水島上等兵は姿を現しません。水島上等兵の竪琴は響いてきません。
兵隊サンたちは捕虜となっていましたので、収容所に収監されている間、様々の雑務をしなければなりません。ある日、彼らは橋の修繕をしていました。すると、そこに何と水島上等兵とソックリな容姿のお坊さんが現れるのです。ビルマは仏教国ですから、お坊さんは沢山います。しかし、水島上等兵にソックリなお坊さんとはどういうことだろう! そのお坊さんは何も口を聞きません。隊員たちは相談し合います。あれは何者だ?水島か? いや、ただのソックリさんだろう。しかしよく似ていたなぁ。そもそもあれが水島だとしたら、なぜアイツが坊主などになるんだ。理不尽甚だしいじゃないか。そうだ!あれが水島ならば、俺たちと面会して無言で通り過ぎるわけがないだろう。
お話の内容はこの程度にしておきましょう。このお話にはどういった意味があるのか。色々な解釈ができると思います。ココでは私の見解を少しだけ記しておくことにします。
このお話は終戦後間もない昭和21年から23年までの間に書かれたものです。戦後三年と経過していません。上に引いた隊長の言葉にある様に「国は廃墟となり」、国民の多くが依然として「手からも足からも力が抜けてゆくような気」から完全に脱し切れてはいない状況のなかでこのお話は書かれました。路頭に迷ったヒトも多くいたはずです。具体的な目的を持てず、将来への目処も立たず、その日その日を生き抜くことで必死なヒトたちも沢山いたはずです。肉親を喪ったヒトもいれば、友人を喪ったヒト、恋人を喪ったヒト、教え子を喪ったヒト、その他無数のものを喪ったヒトで溢れていました。そうした状況のなかで、ある意味では必然的と言るかもしれませんが、戦争に対する怨嗟の故に、人々は非常に過去の記憶を蔑ろにした。政治家を憎み、軍人を憎み、召集された兵隊サンたちまでをも憎んだ。全部ごっちゃにされ、人々の中から死者に対する弔いの想いは稀薄なものとなりかけていた。筆者の竹山道雄氏は後に次のようなことを述べています。
当時は、戦死した人の冥福を祈るような気持は、新聞や雑誌にはさっぱり出ませんでした。人々はそういうことは考えませんでした。それどころか、「戦った人はたれもかれも一律に悪人である」といったような調子でした。日本軍のことは悪口をいうのが流行で、正義派でした。義務を守って命をおとした人たちのせめてもの鎮魂をねがうことが、逆コースであるなどといわれても、私は承服することはできません。逆コースでけっこうです。あの戦争自体の原因の解明やその責任の糾弾と、これとでは、まったく別なことです。何もかもいっしょくたにして罵っていた風潮は、おどろくべく軽薄なものでした。ようやく各地での納骨が行なわれることになったのは、うれしいことだと思います。まことに、若い人があのようにして死ぬということは、いいようなくいたましいことです。(「ビルマの竪琴ができるまで」)
竹山氏はこのお話を書くことで「義務を守って命をおとした人たち」、すなわち無名の兵士たちを鎮魂したかったのだと思います。そして隊長に言わせた様に、死者に少しでも報いることができる様に「共に再建のために働こう」と訴えたかったのだと思います。戦争を遺産とする、と言えば誤解を与えるかもしれませんが、竹山氏は少なくとも次のような想いだけは皆に抱いて欲しいと願いつつ、このお話を書いたのではないかと思うのです。それは──過去を忘れていったいどんな未来がある? 過去を引き受けて、その過去の上に新しい未来を創設していくしかないじゃないか! 過去は切り離せるものではない! 過去は私たちと密接に繋がっているんだ。だとすれば未来だって私たちと無関係にはあり得ないではないか! 過去を忘れたヤツにどんな未来が創れる? 過去を無関係のものとして斥けるヤツは、どうせまたこの先に何かあっても、何食わぬ顔でそこから自己の全てを遊離させるに違いない。責任意識を帰属させようとしない者に、己の仕事を完遂させることはできないだろう。今、私たちは何かをせねばならない。そして本気で何かをするには、全てを引き受ける用意がなければいけない。確かに私たちは多くのものを喪い、そして貴重なものを陵辱したかもしれない。しかし、だからといって、昔を何もかも捨て去れば良いってものではないはずだ。傷跡を直視して欲しい。本当に必要なもの、大切な感情を忘れないで欲しい。そしてそれを胸の奥深くに抱き込んで「共に再建のために働こう」──
このお話は鎮魂の物語であると同時に、同胞に対して向けられた「復活のための序曲」でもあると思います。兵隊さんたちの決意の合唱がここには描かれているのです。その歌が広く国民の間にも拡がることを願わずにはいられない竹山氏の姿を垣間見ることができます。事実、竹山氏はこのお話を次のような一節でもって終わらせています。
船は毎日ゆっくりとすすみました。先へ──。先へ──。そして、われわれははやく日本が見えないかと、朝に、夕に、ゆくての雲の中をじっと見つめました。
戦争が終わって今年で63年が経過しました。終戦間もない頃に「共に再建のために働こう」と決意した人たちも次々と世を去り始めています。「復活のための序曲」はどうなったのでしょう。難しい問題です。けれども、今現在、唯一確実なことは、私たちは今日も何かの歌を、メロディーを、途絶えることなく奏で続けていかなければならないということです。果たして如何なる旋律を選ぶべきか。それは私たちだけではなく、過去に音を奏でた人たちとも相談をしながら、全体の調和を乱さぬよう慎重に決定付けていかねばならない事柄です。というのは、私たちは過去から現在へ、そして未来へと続いていく組曲のなかの一小節を形成するものなのですから。